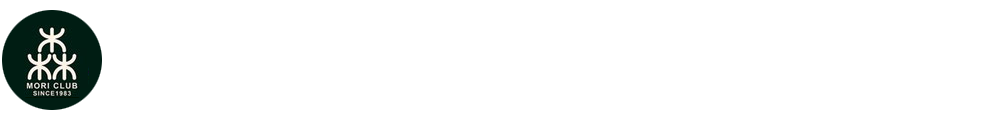5月
10月





九千部山の枯れたブナ




ブナの紅葉

つながってるいきもの
フジミドリシジミ
幼虫がブナやイヌブナを食べるフジミドリシジミというチョウがいます。オスの翅表はメタリックな明るい青緑色、メスは焦げ茶色です。梅雨半ばの時期に出現しますが、佐賀県ではブナのある九千部山だけにいます。脊振山系にもブナはあるのですがフジミドリシジミがいないのが不思議です。温暖化で、山頂のブナの幼木が育たなくなったのが心配です。
フジミドリシジミ成虫


アオスジアオリンガ(蛾)
夏型はアカスジアオリンガに似ていますが、本種は前翅の白帯が平行で間隔が広いという違いがあります。

アトジロエダシャク(蛾)
春にだけ現れる蛾です。

イタヤハムシ
食樹の背が高いので、葉先にいる成虫がなかなか見えませんが、夜よるになると灯火に飛んできたりします。

ウメエダシャク
ウメの木を食べる有名な昆虫の一つはウメエダシャクというガです。幼虫はウメの葉を食べるシャクトリムシです。成虫は昼間ウメの木の周りをヒラヒラとゆっくり飛んで回っています。昔はそう多い昆虫ではなかったのですが、近年は庭に植えたウメなどでもよく見かけられるようになりました。よく似たガにトンボエダシャクがいますが模様が違います。
ウメエダシャク成虫



ウグイスシャチホコ(蛾)
九州ではブナ帯まで標高を上げないと見られません。オスの触角は強い鋸歯状をしています。スズキシャチホコに似ます。

ウスジロトガリバ(蛾)
ブナ帯では必ずと言ってよいほど出てくるガです。

ウスクモエダシャク(蛾)

ウスバミスジエダシャク(蛾)
前後の翅の横脈紋が4つの細長い目のように見えます。オオバナミガタエダシャクに似ていますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では楕円形の紋の中に細長い線状の淡色部があります。裏側の前翅先端部に淡白色の紋がありません。

エゾカギバ(蛾)
表の横脈点てんが無く、色が暗めです。

エゾヨツメ(蛾)

オオヒメハナカミキリ
幼虫はブナの枯れ木を食べ、成虫はコゴメウツギやゴトウヅル・シシウド・ノリウツギなどの花に集まります。

キバラケンモン(蛾)の幼虫

クロツヤミノガ(蛾)

クロテンフユシャク(蛾

コバネカミキリ
夕刻にブナなどの立ち枯れや倒木の朽木に集まります。

ゴマシオキシタバ(蛾

シラホシキクスイカミキリ
カバノキ類・ブナのなどの伐採木に見られます。シラホシカミキリやニセシラホシカミキリによく似ています。

シロオビフユシャク(蛾)

シロシャチホコ(蛾)
本州から九州にかけて分布し、成虫は5~6月と8~9月の年2回見られます。明るく灰色っぽい、そして毛深い印象を持っています。幼虫は驚かせると、典型的なシャチホコガ科の特徴であるシャチホコ型にのけぞります。カバノキ科のアカシデ、イヌシデ、クマシデなどやブナ科、クルミ科、ニレ科、マンサク科、バラ科などかなり広範囲の植物を食べます。
シロシャチホコ成虫

シロシャチホコ終齢幼虫

シロフフユエダシャク(蛾)
2月から3月の梅の花の咲くちょっと前に出てくる種です。最近関東では1月終りから見られるようになってきたそうです。色には白っぽいものから黒っぽいものまで変異があり、メスの体色も灰色から黒まで変異があります。

ナカウスエダシャク(蛾)
ウスバキエダシャク、ウスバシロエダシャク、およびヒメナカウスエダシャクに似ていますが、本種は春~晩秋に出現し低地~山地にいます。前翅は全体に暗く、中央部分がメスでは白。地味なエダシャクの中で晩秋まで残っているのはこの種がほとんどです。


ニワトコドクガ(蛾
幼虫は無毒です。

ヒメシロドクガ(蛾

フクチセダカコブヤハズカミキリ
ブナの立ち枯れや倒木に見つかります。飛べないため歩くのが上手です。

マルモンシャチホコ(蛾
典型的なブナ帯のガです。

ミダレカクモンハマキ(蛾
年1化ですが、幼虫は何でも食べます。雌雄で翅型も斑紋も違うし、幼虫の大きさもオス・メスで違います。
ミダレカクモンハマキの成虫

ミダレカクモンハマキの幼虫

モンキキナミシャク蛾)
ナカモンキナミシャクに似ていますが、本種は外横線が前翅の下側(止まっていると内側)で曲がりません。個体変異は激しい方です。

やってみよう!