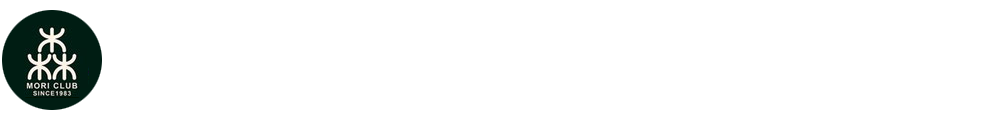4月
10月





エノキの紅葉(2022.11.21 21世紀県民の森〉

つながってるいきもの
ゴマダラチョウ
冬越しした幼虫は春の芽吹きに合わせてエノキに登り、葉を食べて緑色の終齢幼虫になります。まもなく葉の裏で蛹になり、春型の成虫が羽化します。成虫はたいへん果汁や樹液が好きで、クヌギなどの樹液でよく見られます。3回ほど成虫が発生したあと、最後の幼虫は体の色がだんだんと緑色から茶色に変わり、秋の終わりに木を降りて落ち葉の中で越冬します。食樹の枝先で縄張りを張って見張り行動をし、枝先を活発に飛び回るほか、クヌギやヤナギの樹液にも集まります。
ゴマダラチョウ終齢幼虫

ゴマダラチョウ卵

羽化間近のゴマダラチョウ蛹

越冬中のゴマダラチョウ幼虫

樹液に来たゴマダラチョウ成虫

ゴマダラチョウ成虫

ヤマトタマムシ
玉虫厨子に一面埋め込まれているのはこのヤマトタマムシの翅です。金緑色に赤い筋が入るその翅はため息が出るほど美しいです。昔はこのたま虫の死骸をタンスに入れておくと着物が増えるという言い伝えがあったそうです。幼虫はエノキ、ケヤキなどの枯れた部分を食べ、成虫はよくエノキやケヤキの枝先で翅をきらめかせて飛び回ったりします。
ヤマトタマムシ成虫

ヤマトタマムシの脱出孔

アカバキリガ(蛾)
幼虫は怒らせるとギシギシ鳴きます。幼虫はミツボシキリガに似ています。

アシナガオニゾウムシ
成虫は枯れたエノキなどにあつまります。オスは長い前脚をもっており、ほかのオスとよくケンカをします。地味な色をしており、枯木の幹にじっととまってればなかなか見つかりません。

ウスバツバメ(蛾)
繭は主葉脈の上に必ず作るようです。体の周りに糸を張って繭の基礎を作り、それに体液を染み込まして固めます。表面には凸凹の脆い殻が被り、これには外側の殻にのみ穴が開いており内側は硬い殻で守られています。
ウスバツバメの成虫

ウスバツバメの幼虫

ウスバツバメの繭

ウスバフユシャク(蛾)
ヤマウスバフユシャク、クロテンフユシャクに似ますが、本種は前翅外横線が緩やかなカーブを描きます。止まったとき左右のどちらが上になるかは、その都度変わるようで、決まってはいません。


エノキハムシ
公園や町はずれの小さなエノキでも成虫や幼虫が見つかります。葉に穴をあけて食べますから、そのような食べ跡を探すと見つかります。
エノキハムシの成虫

エノキハムシの幼虫

オオシマカラスヨトウ(蛾)
オオシマカラスヨトウの成虫

オオシマカラスヨトウの幼虫

オオシロカミキリ
平地から山地まで生息していますが、神社の大きなエノキなどに発生し、付近の灯火に飛んできているのが見つかったりします。

クスサン蛾)

クロスカシトガリノメイガ(蛾)

クロテンキリガ(蛾)

ウチムラサキヒメエダシャク(蛾)
クロフヒメエダシャクに似ています。

シータテハ
暖地では山地性で分布地はそう多くないです。渓流沿いの林縁部で見られ、成虫越冬します。
シータテハの成虫


シータテハの幼虫

タカオシャチホコ(蛾)

テングチョウ
基本は年に1化ですが、エノキの不定期の芽吹きにより時季外れの産卵が行われ複数世代を繰り返します。成虫越夏・越冬。
テングチョウの成虫

テングチョウの幼虫

テングチョウの蛹

ドロハマキチョッキリ
カエデの葉などをしおれさせて産卵します。枝先の若い葉がしおれていたら探すと見つかります。とてもきれいな色をしています。緑の体ですが赤っぽい光沢と金色っぽい光沢の二通りの色がいます。

ナミガタエダシャク(蛾)

ナミガタチビタマムシ
冬場に主にムクノキの樹皮をはがすと集団で成虫越冬しているのが見つかります。ヤノナミガタチビタマムシにそっくりです。

ニレキリガ(蛾)

ヒオドシチョウ
年1化。成虫で越冬。樹液に集まります。
ヒオドシチョウの成虫

ヒオドシチョウの幼虫

ヒオドシチョウの蛹

ヒシモンナガタマムシ
エノキの伐採木に集まったり、ケヤキの樹皮下で成虫越冬するのを見たりします。

ヒメゴマダラオトシブミ
エノキの葉をさがすと成虫は見られますが個体数は少ないです。よく似たゴマダラオトシブミを少し黒っぽくした感じです。
ヒメゴマダラオトシブミの成虫

ヒメゴマダラオトシブミの揺籃

ホソウスバフユシャク(蛾)
Inurois属では冬の最後の方に出現する種。冬の終わりを告げる蛾です。

モクメクチバ蛾
春にちょっと擦れた個体が見られることが多いです。

ヤノトラカミキリ
成虫はエノキやエゾエノキの伐採木、衰弱木に見られます。

ワモンサビカミキリ
伐採枝を積んであったりするとよく見かけます。

やってみよう!